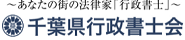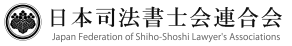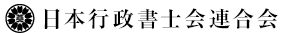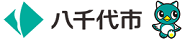2021/10/27作成
前回、前々回からのつづきで、「相続土地国庫帰属制度」のお話です。
何度も申し上げておりますとおり、国もタダで貰ってくれる訳ではなく、〝相続した土地を手放したい〟と法務局へ申請して要件審査をクリアし法務大臣の承認を受けられた場合(国が土地を貰い受けることをOKした場合)、承認を得られた者は、その土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を国へ納付する必要があります。それでは、その「土地管理費相当額」とはどれくらいなのでしょうか?
■「その土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額」とは?
参考として挙げられている金額は、「現状の国有地の標準的な管理費用10年分を参考に、粗放的な管理(大まかな管理でOK)で足りる原野が約20万円、市街地の宅地200㎡が約80万円」となっています。承認申請者が負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付しないときは、承認の効力は失ってしまいます。30日以内にきちんと納付した場合には、その納付時に承認された土地の所有権は国のものとなり、国のものとなった土地は財産として、国が管理・処分します。
■「土地の具体的管理機関」はどこ?
・主に農用地又は森林として利用されている土地については
→農林水産大臣が管理・処分
・上記以外の土地については
→財務大臣が管理・処分
以前から、相続した土地が「自分の住まいから遠方すぎてその管理ができない」「相続した土地のみでは利活用が困難で、且つ、その土地のみでは売買や贈与などの譲渡処分も難しい・・地元の市区町村に寄付できないか?」など、せっかく相続した土地にも関わらず、積極的に手放したい又は手放す方法は何かないかと言ったご相談をお受けすることがしばしばありました。
今回新しく成立したこの〝相続土地国庫帰属法〟が相談者の悩みの解決の一翼を担ってくれることを願うばかりです。